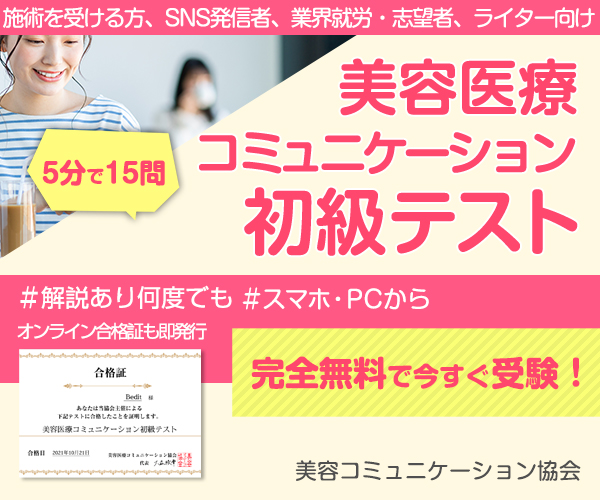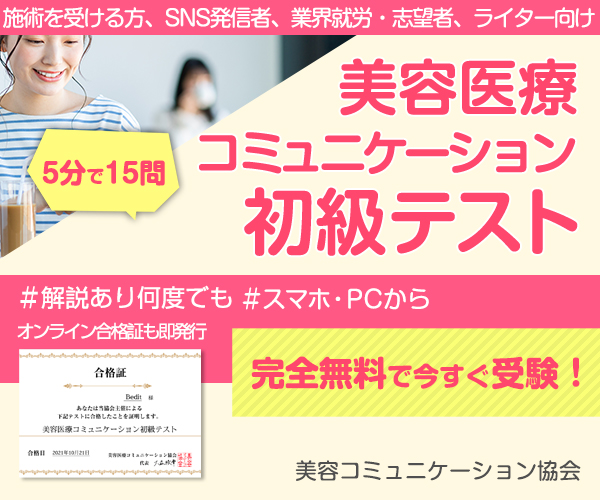

※写真はイメージです。
オーバーラップする二人のジャンパー
「レジェンド」葛西紀明は2014―2015年シーズンを順調に終えた。W杯第3戦で自身通算17勝目となる優勝を飾り、自ら持つ最年長優勝記録を42歳5ヶ月に伸ばした。
精神的、肉体的にきついジャンプ競技は、30歳台になると引退がささやかれる。
なのに40歳代になってもさらなる新たな挑戦へと自らをいざなう。
何をもって葛西にそうさせるのだろうか?
それを考えると、私は葛西の先輩にあたる一人の男を思い出す。
秋元正博――。
秋元はレークプラシッド五輪において、たった50cmでメダルを逃したジャンパーだ。
その後、様々な苦難を迎えながらも、五輪のメダルにこだわリ続けた男である。
葛西にしろ秋元にしろ、果たせなかった夢や、心残りが、選手のモチベーションを常人以上に高めるのではないだろうか?
ソチ五輪の驚き。「銀」より「金」
2014年のソチ五輪のあの日、テレビでかじりついていた私は本当に驚いた。
41歳にしてラージヒル銀メダルに輝いたスキージャンパー葛西紀明は躊躇なくこう宣言したからだ。
「次は金メダルを目指します」。
私が新聞社のスポーツ記者をしていた当時、初めての海外取材は1989年の世界選手権ラハチ大会だった。
そのラハチ大会に16歳8ヶ月で日本人男子史上最年少で出場したのが葛西だ。
日本ジャンプ陣低迷期に現れた、若きホープだった。
その後、葛西はW杯に優勝、世界選手権でもメダルを獲得するなど、日本のエースに成長している。1994年のリレハンメル五輪で団体銀メダルを得た。
そうして2014年、世界に挑戦して25年目にして初めて得た個人の銀メダル。
「よくぞ、やった」「頑張った」「ご苦労様」と、日本全国の思いは同じだったと思う。
ところが、NHKのインタビュアーに葛西は競技続行どころか、4年後の金メダルを狙うことを宣言したのだ。
「なぜ、そこまで?」。
思わず、耳を疑った。聞き間違いかと思った。
どうして、葛西はそこまで自分自身を追い込むのだ?
メダル最有力候補だった秋元
1980年レークプラシッド五輪のジャンプ70m級(現在のノーマルヒル)で、秋元正博はメダル最有力候補だった。
しかし、結果は4位。表彰台を逃す。
秋元の飛距離は、83.5m、87.5m。飛型点を加えた合計得点が248.5点。
同僚の八木弘和が87m、83.5m、東ドイツのデッケルトが85m、89mと共に249.2点で並び、銀メダルを分けあった。
秋元の明暗を分けたのはわずか0.7点、当時の得点方法によると飛距離にして50cmの差だ。このわずか50cmで秋元はメダルを逃した。
この時、メダルを獲得していれば、秋元の競技人生は変わったかもしれない。
暗転から運命のいたずら
4年後の五輪を目指した秋元正博にアクシデントが起こる。
1982年、北海道瀬棚町で運転中、交通死亡事故を起こしてしまう。
1年間の試合出場停止処分が下され、秋元は練習時間もとれず、所属していた地崎工業の現場で働いた。
1983-1984年、サラエボ五輪のシーズンに秋元は謹慎を解かれた。
しかし、国内大会に限って出場しても良いという条件付きだった。
『ならば、五輪は出場できないのか?』。
あいまいなスキー連盟の裁定の中、秋元は意地を見せつけるかのように、シーズン当初から優勝、上位をキープした。
だが、結果的にサラエボ五輪は秋元本人から出場辞退を申し出た形になった。
スキー連盟、JOC、文部省などの筋から圧力があった、とも言われているが、本人は一切口を閉ざし、今も話そうとはしない。
ちなみにサラエボ五輪で日本勢は、90m級(現在のラージヒル)で八木の19位が最高と惨敗している。
「世界」を見据えてW杯優勝
翌シーズンも、秋元正博は国内大会で連勝を続けた。
目標としたのは優勝ではなく、得点だった。
国内で優勝しても「今日の得点なら、せいぜい世界で10位」。
「この得点だったら、なんとかトップを争えるかもしれない」。
秋元は得点を通して、見えない世界の敵と国内で戦っていた。
そんな時、「世界」のチャンスがやってくる。
海外遠征に出れない秋元にとって、札幌で開催されるW杯は世界と戦える唯一の場所だ。
1985年2月の札幌大倉山のW杯は、前年サラエボ五輪の90m級金メダリスト、マッチ・ニッカネン(フィンランド)、同銀メダリスト、イエンス・バイスフロク(東ドイツ)が参加した。
ちなみに70m級の金がバイスフロクで、銀がニッカネン。
まさに当時の2強だ。
大会で1本目を終えて、秋元は7位。
2本目を迎えた時、雪が激しくなり、まともにジャンプをできない選手が続出した。
だが、2強ですら失速する中、秋元だけが飛距離を伸ばし、見事に大逆転で優勝した。
世界の2強を抑えてのW杯優勝は価値がある。
「サラエボに秋元が出ていれば・・」。
大倉山シャンツェで私の頭をよぎった思いは、その場の誰もが思ったはずだ。
フライング選手権で大転倒
晴れて海外遠征も解禁となった1985-1986年シーズンの後半、秋元をまたもアクシデントが待ち受けていた。
1986年3月、バットミッテルンドルフ(オーストリア)で開催されたフライング世界選手権で、空中に飛び出した秋元を突風が襲う。
右足スキーが大きく巻き上げられ、秋元はつんのめるようにランディングバーンにたたきつけられた。そのまま2度、3度バウンドして、滑り落ちた。
長いスキー板が秋元の右足首にからまるように回転した。右足首複雑骨折の重症だった。
選手生命の危機
右足首の骨折はジャンプ選手にとって致命的だ。
医師によれば、粉々になった骨の破片をつなぎ合わせるような手術だったという。
まして、一度転倒してしまうと通常、ジャンプ選手は恐怖感から飛べなくなる。
周囲はすでに秋元の競技続行を諦めた。
そんな中、本人は「オレはまた飛ぶ」と言い切った。
どんな顔して見舞いにいっていいのやら、私は重い気持ちで病院に向かった。
足をつって、包帯だらけで寝ていた秋元は私に言った。
「やっちゃったよ」。
苦笑いを浮かべる秋元には悲壮感がなかった。
執念の復活
激しいリハビリに耐えた秋元は、驚くべきスピードで復活への階段をかけ上がる。
怪我から半年後の、1986年の11月には雪上のトレーニングを開始した。
この時、北海道下川町のジャンプ台で、秋元は「オレよりうまい中学生がいる」と私に教えてくれた。それが、葛西紀明だった。
秋元が言うには、踏み切りから空中に移る体重移動は天性のものらしい。
葛西はその後、東海大四高を経て、秋元のいた地崎工業に入っている。
秋元は、なんとこの1986―1987年シーズン最後の大会で復帰に間に合わせた。
1987年3月、シーズン終わりの2連戦で出場したばかりか、一線級の選手が出場した宮様スキー大会で3位に入り、続く伊藤杯ナイタージャンプでは優勝と、文句のつけようがない復活をアピールした。
今思えば、当時の秋元の頭の中には、1988年のカルガリー五輪があった。
間に合わすためには、このシーズンでなんとしても復活する必要があったのだろう。
最後の望みも絶たれ
翌1987―1988年シーズン。
秋元にとって、目指すのは「50cmで逃したメダル」の五輪代表だ。
だが、骨折の後遺症は残っていた。
右足首は左足首ほど前傾できない。
普通、前に45度ほど曲がる足首がせいぜい20度しか曲げられない。
リハビリを続けても、どうしても元に戻らない。
クラウチング姿勢で滑走し、空中に踏み切るジャンプにとって、足首が前傾できないのは致命的だ。
どうすればいいか?
秋元は右足の靴の下に台を作り、右足首の前傾の不足を補おうとした。
クラウチング姿勢は右足と左足を少しだけ前後にずらし、左右の前傾の差を補う工夫を考え出した。
私はシーズン開幕を迎えた北海道名寄市のホテルのスキー置き場にいる秋元に会った。一人でノコギリで木材をカットしていた。
「何してるの?」と問いかけた。
「実はさ・・・」と秘策を話してくれた。
シーズンぎりぎりで、下した決断だった。
話を聞いた私もやすりを持って手伝った。微妙に異なる角度の角材をいくつか作成した。
秋元最後の戦いとなってしまった。
翌年1月中旬の五輪選考会まで上位をキープした秋元だったが、ジャンプに全盛時の鋭さは戻らなかった。結局代表には選ばれなかった。
秋元正博は翌1988―1989年シーズンで引退する。
もはや、かつてのジャンプを飛べる身体ではなかった。
長野五輪の傷心
葛西紀明にとって、いまだに後悔が残るのは1988年の長野五輪だ。
長年に渡って、日本のエースとして海外でも活躍した葛西だが、なぜか長野五輪のシーズンは不振だった。
五輪代表に選ばれたものの、個人戦ノーマルヒルは7位。
ラージヒル、団体戦からはメンバーから外れた。
日本は団体戦で原田雅彦の起死回生大ジャンプや、船木和喜が最後を飾ったアーチで金メダルに輝いた。
金メダルの瞬間、葛西がジャンプ台から消えるように去った姿を見た人は少ない。
葛西の挑戦は続く
ソチ五輪の銀メダルにも、葛西の心は満たされていなかった。
50cmでメダルを逃し、交通事故、謹慎、骨折を経てもなお、五輪にこだわった秋元正博。
W杯、世界選手権などで好成績を挙げながらも、五輪で金メダルととれなかった悔しさを忘れない葛西紀明。
やり残した思いほど、アスリートを奮いたたせるものはない、のかもしれない。
キング・カズこと、サッカーの三浦知良、2つの金メダルに輝きながらさらに現役続行を宣言した平泳ぎの北島康介、しかり。
葛西紀明は2017年韓国・平昌五輪での金メダルを実現するだろうか?
一番、楽しみにしているのは秋元正博かもしれない。