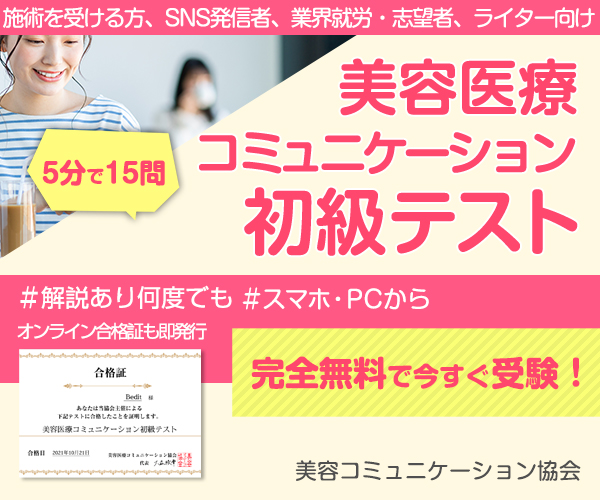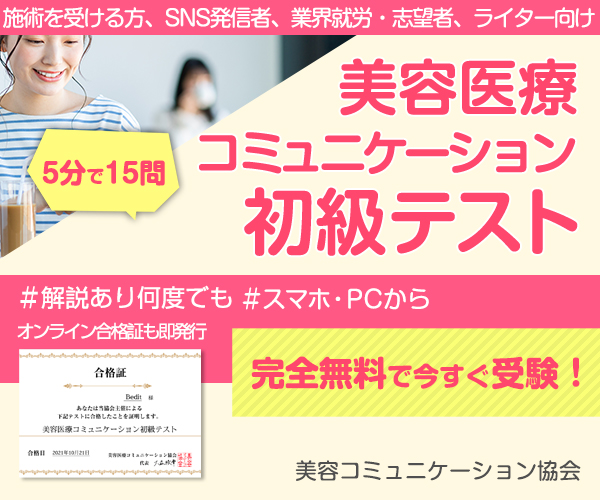

※写真はイメージです。
記録映画ではない記録映画
1965年3月20日、前年の1964年に開催された『東京オリンピック』の公式記録映画が東宝系で劇場公開された。
この公式記録映画『東京オリンピック』は今でもDVDで観ることが出来る。
結論を先に、批判されることを覚悟で言うのなら、「これは純然たる記録映画ではない」。
申し訳ないが、はっきり言って僕には「よくわからなかった」。
ただし、そう、思ったのは僕だけではないようだ。
文庫『TOKYOオリンピック物語』(野地秩嘉/2013年10月13日/小学館)に、そのことが書かれている。
公式記録映画『東京オリンピック』を、試写会で観たグラフィックデザイナー・亀倉雄策氏は「映像美は素晴らしい」と思ったという。
しかし、当時、同じように試写会で観た、前オリンピック担当大臣・河野一郎氏は、この映画を痛烈に批判している。
「映画は芸術だが記録じゃない」「俺にはちっともわからん」そう言ったのだという。
「記録性をまったく無視したひどい映画」と切り捨てた。
この発言は、有識人や報道にまで波及して論争を巻き起こした。
配給元の東宝はさまざまな非難に遠慮して総監督・市川崑氏に一部手直しを要求している。
僕が観た公式記録映画『東京オリンピック』はその手直しされたバージョンなのだが、それでも、河野一郎氏と同じく「ちっともわからん」と言いたくなる。
当時、「芸術か記録か」の論争が巻き起こったというこの、公式記録映画『東京オリンピック』だが、そもそも市川崑氏は記録映画を作るつもりはなかったのだろう。
文庫『TOKYOオリンピック物語』(野地秩嘉/20134年10月13日/小学館)には、この公式記録映画の製作秘話が綴られていてとても興味深い。
撮影スタッフのひとりだった助監督・亀田佐氏は市川崑氏にドキュメンタリーと劇映画の違いについて尋ねたという。
すると市川氏は、「『劇映画は役者を演出する、ドキュメンタリーは場を演出する』とおっしゃった。続いて、ドラマはアクションを撮る、ドキュメンタリーはリアクションを撮る」(談・亀田佐『TOKYOオリンピック物語』)と言ったという。
さらに亀田佐氏は「ドキュメンタリーでは選手を動かすことはできません。ですから、選手が走る前の緊張感、走った後の安堵した表情を撮ることが、ドキュメンタリーにおける市川さん流の演出だと思いました」(談・亀田佐『TOKYOオリンピック物語』)とコメントしている。
また、脚本を担当した谷川俊太郎氏も「崑さんは、始終、この映画では人間を描くと言ってました。スポーツを描くよりも人間を表現すると強調していました」(談・谷川俊太郎『TOKYOオリンピック物語』)と発言している。
市川崑氏はスポーツについて詳しくなかった。用語やルールも知らなかった。陸上の100メートルを「かけっこ」と言った。
しかし、スポーツに詳しい、詳しくないではなく、映画監督して、単なる記録映画ではないドキュメンタリー映像を作ろう、そう思ったに違いない。
確かに記録映像だけをつなげれば、誰もが思う記録映画にはなる。しかし、そんな映画で人は感動はしない。
純然たる記録映画は、言ってみればかなりマニアックな映画であり、一般受けすることはない。
純然たる記録映画で良いのなら総監督として市川崑氏を起用する意味もない。
つまり、「公式記録映画」だと思ってみるから期待を裏切られたような気になる。
はっきり言って「記録映画としては、よくわからなかった」が、「映画として興味深くは観れた」、と言い方を訂正しよう。
それは公式記録映画『東京オリンピック』が、観客を楽しませるようにいろいろと工夫がされているからに他ならない。
総監督・市川崑氏とニュース映画社の精鋭たち
試合だけを撮るキャメラマンはいらない、それが市川崑氏のポリシーだった。
市川崑氏が撮りたかったのは試合の結果より、人間だった。
選手が何を考えているか?を描こうとした。
国を背負うことのプレッシャー。記録への挑戦。そこにドラマがある。
走り高跳びでは、アメリカのトーマス選手とソビエトのブルベス選手の一騎打ちにスポットを当てた。
砲丸投げでは、競技そのものより選手のしぐさや表情。神経質にテンションを高める選手の姿を映し出す。
棒高跳びでは、7時間を経過し暗闇の中で行われた、アメリカのフレッド・モーガン・ハンセン選手の優勝に至るまでを劇的に捉える。試合終了後のドイツのラインハルト選手がクシで髪を直すのが、「やはりオリンピック選手も若者なんだな」と思えて印象的だ。
開催中、いつも晴天に恵まれていた、というわけではない。雨の日の国立競技場、雨でびしょ濡れになってもオリンピックを支え続けるスタッフを映し出す。
男子10000m決勝。日本の円谷幸吉選手を応援する人々にスポットを当てる。オリンピックというよりまるで運動会のような観衆。
ラスト走者となったセイロンの選手も写す。主役は優勝した選手だけではない。倒れ込み負傷した選手も写し、オリンピックの過酷さを観せる。
観客席で見守る野球選手の長嶋茂雄氏と王貞治氏もいる。
各国の報道陣、プレスセンター、タイプを打つ報道陣。そんなところにまでもスポットを当てる。
市川崑氏の要望を見事に実現させたのはニュース映画社の現場スタッフだった。
ニュース映画社のスタッフたちは、さまざまな競技のテスト撮影をして準備をしていた。
ある者は海外に行き、オリンピックに出場し、メダルが有力視されている選手に取材をした。
ニュース映画社のスタッフたちは誰もが、スポーツ競技を撮るにためには、事前の下調べが重要だと考えていた。
助監督の亀田佐氏は、「この選手は左から跳ぶ。バーまでの助走は何歩で走る。その後、踏み切るから足のアップを撮るなら、助走路のあのあたりにレンズを合わせろ」(談・赤津光男『TOKYOオリンピック物語』)そう、スタッフに指導したという。
一度しかない本番のために下調べを繰り返した。