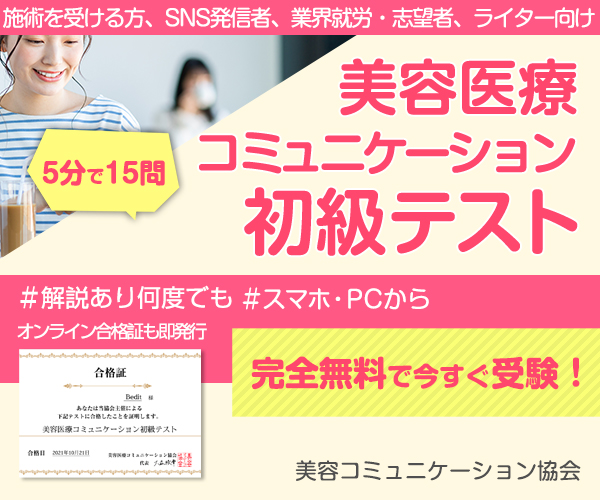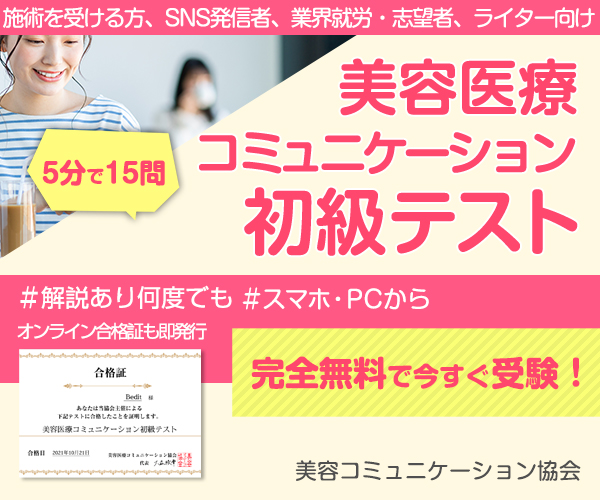

※写真はイメージです。
なぜ人はさまざまな人格に粉砕されてしまうのか?
「僕が暴れ出すと母が包丁を持ち出して「これで私を殺しなさい!」と怒鳴ることもよくあった」(後藤浩輝『意外に大変。』東邦出版)
『ジェニーのなかの400人』という本がある(ジュディス・スペンサー 早川書房)。
母親により2歳で悪魔崇拝のカルト教団に入れられたジョニーは、34歳になり、初めて医師による治療を受けるが……。
短いカウンセリングでも次々に人格が入れ替わる。ジェニーは400もの人格に粉砕されていたのだ。
生まれたときの人格「ジェニー」はタマネギにアレルギー反応を起こすが、ロック好きの反抗的ティーンエイジャーである「セリーナ」が現われるとタマネギを貪り食う。「セリーナ」は低い声でロックを歌うが、28歳の「フリージャ」が現われると、きれいなソプラノでオペラを歌う。
400人のなかには84歳の「スー伯母さん」という人格もあり、家にひとりで取り残された「ジェニー」(あるいは他の人格)にこう告げる。
「辛いことはみんな夢のなかの出来事なの」
なぜ、人間はさまざまな人格に粉砕されてしまうのか?
『ジェニーのなかの400人』(ジュディス・スペンサー 小林宏明訳 早川書房)
驚いた。父が「落ちてきた」のである。
後藤浩輝騎手は自伝『意外に大変。』(東邦出版)の後半で自らの生い立ちを赤裸々に語っている。
<ある日のことである。僕は地域の少年野球クラブに入っていて、その日は練習日だった。夕方まで練習し、疲れて家に戻った。「今日の晩御飯はなんだろう」なんてことも考えていたかもしれない。家に着き、「ただいま」と言って家のドアを開けた。その瞬間、目の前に父が落ちてきた>
後藤騎手の両親は離婚していた。姉は母の元にとどまり、後藤騎手は父と二人暮らしを始めていた。
<驚いた。父が「落ちてきた」のである。一瞬、状況がまるでわからなかった。なぜ父は落ちてきたのか。それよりも、父が落ちてくるという状況は、いったいなんなんだ。僕は父が落ちてきた方向、つまり上を見て、なにが起こったのかを理解した。
父は、首を吊ろうとしていたのである>
離婚後、時をおかず後藤騎手の母親は再婚した。「姉と自分は父親が違う」という状況を後藤騎手は認めることができなかった。
<とにかく父は自ら命を絶とうとしたのである。子どもである僕が、それを理解できるわけがなかった。父が自殺しようとしたという衝撃だけが僕を襲った。
僕は泣き喚いた。僕を見て父は「すまん」と謝った。僕は「自殺なんて考えないでくれ」とひたすら泣き続けた。父も、自分のしようとしたことに後悔しているようだった>
テレビや雑誌でコメントする心理学者や精神科医は、したり顔でこう解説するかもしれない。
「このとき、後藤騎手のなかで別の人格が生まれたのではないか。耐えられない苦痛に対し、苦痛を耐えることができる人格が生まれたのかもしれない」
話はこれで終わりではない。後藤騎手の身に次に起きた出来事を知れば、コメンテーターの「憶測」は「確信」に変わるのかもしれない。
父が無理心中をしようとしているのがわかって、僕は抵抗ができなくなった。
<しかし、これだけでは終わらなかった。その日からまだ何日も経っていないある夜のことである。僕はすでに床に入って寝付いていたのだが、突然、息苦しくなって目を覚ました。呼吸ができず、とにかく苦しいのだ。なぜそんなことが起こったのか、咄嗟には理解できなかったが、目を開けたときに恐ろしい事実を知った。父が、僕の首を絞めていたのである>
自殺未遂。そして、無理心中。
<僕は瞬時に父の考えていることを理解した。「一緒に死んでくれ」。何日か前の一件を考えればそれしかない。父のなかではまだ、死の衝動が強く残っていたのだ。あのとき泣き喚いた僕を一人残していくことが不憫になったのか、それとも自分が死んだあとに僕が母に引き取られることがつらかったのか……。ともかく、父が無理心中をしようとしているのがわかって、僕は抵抗できなくなった>
このときの後藤騎手の心の内は、おそらく、誰にもわからないだろう。
<怖くて怖くてもう目も開けることができない。身体は完全に硬直してしまっていた。このまま死んでいくんだろうなという思いと、それに対する恐怖しか僕のなかにはなかった。だんだんと意識が薄れていき、どうすることもできなかった。本当に死んでしまうのか……。死を覚悟したというより、諦めの境地に近かった>
このときの後藤騎手の気持ちは誰にもわからないが、ひとつだけ確かなことがある。
死のことなど一片も考えていない小学4年の後藤浩輝は、父の両手によって「死」をその体内深くに埋め込まれてしまったのだ。
<そのとき、首に絡みついていた手から力がふっと抜け、呼吸ができるようになった。思い止まったのである。あのとき父がそのまま手を緩めなかったら、僕は今ここにいない>
落馬事故を目にするたびに私は思う。
「これは宿命なのか?」
競馬騎手の勝負服には「死にゃあいいんだろう」といったようなヤケクソの諦念が張りついている。