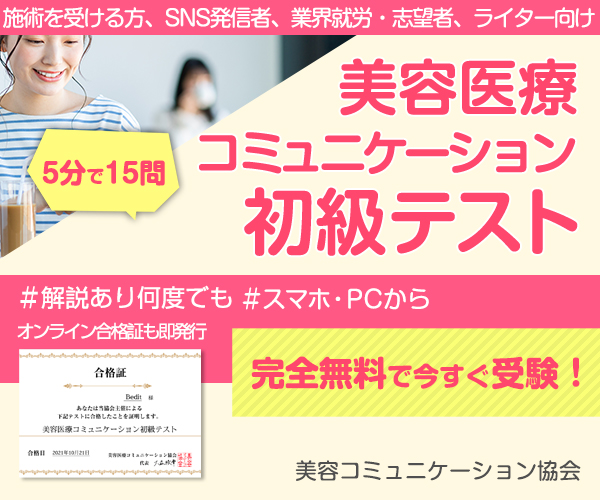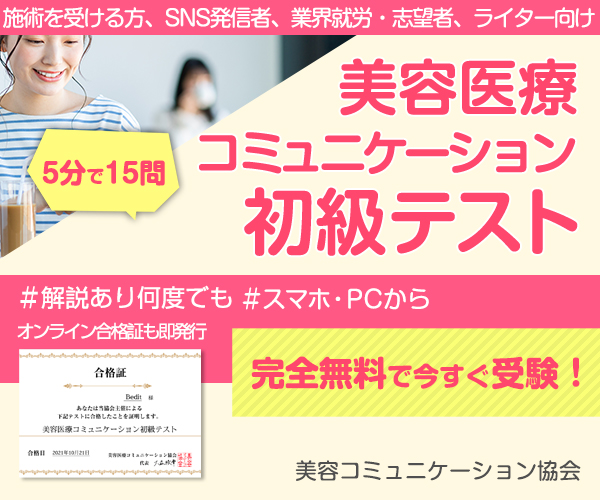

※写真はイメージです。
見えてきたのは、ほんのちょっと前の自分だった
合気道の達人、藤平光一の指導を受けるようになって、「天才」榎本喜八のバッティングは好調時のそれに戻った。
地を這うような打球がそのままスタンドへと吸い込まれていく――それが榎本喜八だけが演じられる魔法、「一代の芸」。
<それでも打ち損じをすることがある。すると、「この野郎!」と思って、がむしゃらにバットを振った。そうするとバットは自分の思い通りの軌道を描かず、わずかにボールの芯をはずれた。>(松井浩『打撃の神髄』講談社)
がむしゃらに練習する。ひたすらバットを振り続ける。
「1万回素振りをしろ、と言えば、本当に1万回バットを振るやつ」――度が過ぎる「マジメ人間」榎本喜八は、先輩から笑われ、同時に恐れられていた。
<こんな状態が三、四球も続くと、ふっと藤平のおだやかな顔が浮かび、改めてバッターボックスの中で藤平に教えてもらった「重みは下」という言葉を心の中で唱えてみる。そうすると、また火の出るような鋭い当たりがよみがえり、雑木林のなかへ消えていくのだった。>
それまでの榎本は、「がむしゃらにバットを振れば状態は戻る」と漠然と考えていたが、現実はまったく逆だった。
<「そのうち、打ち損じをしてカッカすると、臍下の一点に沈めた気持ちが顔までのぼっているのがわかるようになったんです。臍下に収めたはずの気持ちが、顔のあたりまで上がって熱を持ってる。気持ちが焦った時、自分の顔がカッカ、カッカと熱くなるのは、そのためなのかと思いましたね」
そして、自分の気持ちが顔に上がった時には、決まって肩も上がっていた。
「なるほど、これが、肩に無駄な力が入った状態なんだな」>
肩に力が入り、足からではなく肩から体を回転しバットを振ってしまう。榎本喜八の最大の悪癖がこれだった。
「臍下の一点」という「気持ちをしずめる場所」を知ることで、榎本は「不調時の自分」を客観的に見ることができるようになった。
ストレスから「動物虐待」までやるようになった男を救った「呼吸法」とは?
このとき、榎本喜八が取り組んでいたリラクゼーションは「呼吸法」だった。順を追って解説しよう。
(1)息を吸う。頭のなかに空気がいっぱいに詰まっている、とイメージする。
(2)その空気をできるかぎり静かにゆっくりと鼻と口から吐き出している、とイメージする。
(3)頭のなかの空気を吐いたら<顔→首→手→腕→胴体→腰→脚→足→つま先>この順番で「吐き尽くす」。
(4)鼻から空気を吸う。
(5)まず、つま先を空気で満たす、とイメージする。
(6)つま先が空気でいっぱいになったら<足→脚→腰→胴体→腕→手→首→顔→頭>この順番で空気を満たしていく。
(7)頭のてっぺんまで空気でいっぱいになったら、「臍下の一点」に無限にしずめる、とイメージする。
榎本喜八にとって、この「呼吸法」は効果てきめんだった。「ガマガエルを空気銃で撃たないと落ち着かない」というストレスフルな日常を生きていたのだから当然である。
合気道の極意「臍下の一点に心をしずめ五体を結ぶ」
次に榎本喜八が取り組んだのは「五体を結ぶ」トレーニングである。
これは通常、「座禅」か「リラックスして座った状態」で行うもの、と私は考えていたが、榎本はバットを構えた状態で試みたという。
まず、「臍下の一点」から血液が流れ出ていく、とイメージする。それが「つま先まで」「手の指の先まで」「頭のてっぺんまで」流れていく、とイメージする。
意識の中心は「臍下の一点」に置いたまま、血流によって「五体を結ぶ」わけである。
しかし、投手との対戦は「阿吽の呼吸」。相撲でいえば「立ち会い」である。榎本がバットを構えると、すぐさま投手はボールを投げ込んでくる。
この一瞬で五体を結ばなくてはならない。
当然、最初は素振りの際に時間をかけて行った。
五体の隅々に血液が行き渡った、と感じるまで待ち、バットを振る。
これを何百回と繰り返していると、突然、知覚が劇的に変わった。
バットがズンと重くなったのだ。
「あれ? バットってこんなに重かったかなあ」
普通のバッターがそう感じたら、「疲れている」と思うはずだが、榎本は違った。
「この重いバットを早く振りたい」
<ペナントレースが開幕して、梅雨の時期になると一回目の疲れのピークがやってくる。その頃にはバットが重くてね。それでも三割を打ちたいという一心でバットを振ってきた。そして、こういう時期に耐えてバットを振ってこそ、本当の練習だと思ってた。それが、この時はバットが重いのに、バットを振りたくて仕方ないんだからねぇ。実際に、その重みを二の腕の下に感じながらバットを振ると、自分でもビックリしちゃうぐらいの振りができたんですよ」>
しかし、これは前兆にすぎなかった。
榎本喜八、山内一弘という「二枚看板」がそろって不調。大毎オリオンズは4位で1959年のシーズンを終えた。4番打者にも起用された榎本の打率は.276。「A級戦犯」とヤジられても言い返せない成績だった。
東大グラウンドで打撃練習をしていたとき、榎本喜八は一度構えたバットを下げてまじまじと見た。
今まで経験したことのない感覚だった。
バットを構える。投手の方を見る。
目はバットから大きく離れているのに、榎本にはバットが見えた。ちらっと見えた、のではない。ヘッドからグリップエンドまでバットの全体像がはっきりと見えている。
榎本喜八は目で投手を見つめ、頭でバットを見ていた。