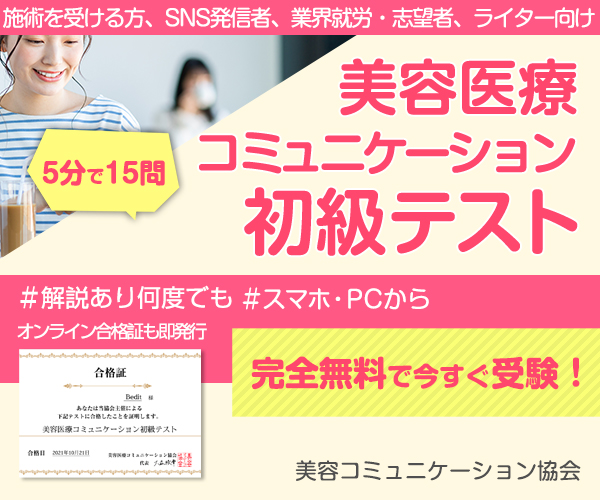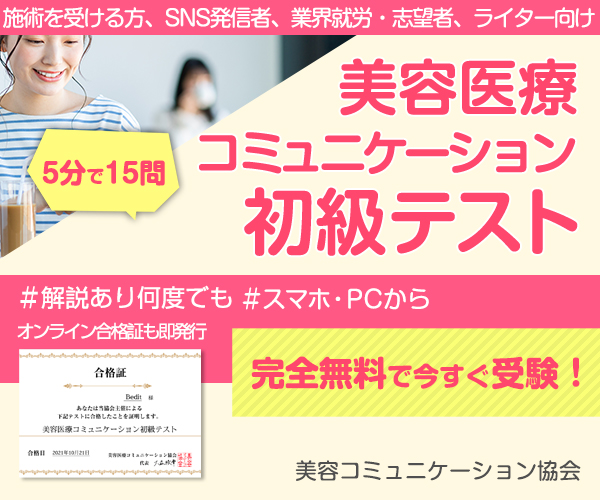

私はグレート東郷の用心棒として雇われた(大山倍達)
大山倍達の空手の師、曹寧柱は、マス・トーゴーのアメリカ遠征についてこう語っている。
<大山はプロレスをやりにアメリカに行ったわけではないけど、東郷の側に付くという役目もあったわけですから>(『大山倍達正伝』)
「側に付く」とは?
<一度や二度は必ず実戦をしなければならない場面があるに違いないと……。>
「実戦」とはプロレスの試合のこと?
<そのときのために、私は徹底的に目突きと金的蹴りを稽古させたんです。>
プロレスでは目突き、金的蹴りは禁じられている。反則技。
大山と行動を共にした「コウ・トーゴー」こと遠藤幸吉は言う。
<東郷が自分のボディガードじゃないけど、とにかく強烈にアピールできる人間を自分のそばに置いとく方がいい、ということで(大山は)抜擢された。>
グレート東郷の体の傷は、リングで負ったものより、怒り狂った客の刃物によって刻まれたものの方が多かった、といわれている。
大山倍達自身の言葉。
<私はそもそも東郷先生の用心棒として雇われてアメリカに渡ったんだもの。>(『大山倍達正伝』)
マス・トーゴーの役割は、暴漢からグレート東郷を守ること。これは確かだろう。
<アメリカで空手を実演して広めるのが目的だったことは事実だよ。でもね、当時の私は食い詰めていて、とにかくお金に困っていたのよ。>
グレート東郷は「未知のテリトリー」に初侵攻した?
大山倍達はシナリオのある「インチキのショー」などやるつもりはなかった。いや、「やりたくない」以前に「できない」。
ではなぜ、大山は生涯、「プロレスラーと闘ってノシた」ことにこだわり続けたのだろうか?
私が注目するのは、40歳を過ぎたばかりの「同級生」レスラー、グレート東郷とディック・レインズがミネアポリス郊外で「初対決」した事実である。
グレート東郷は西海岸を主戦場としていた。
ミネアポリス地区について、ルー・テーズはこう書いている。
<アイオワでサーキットをスタートして4カ月ほど経った頃、プロモーターのP・ジョージの事務所に呼び出され私はこう言われた。「随分君も強くなってきたし、このままアイオワに留まっていたら君のためにもなるまい。きのうミネアポリスのトニー・ステッカーから電話をもらって、是非君を使ってみたいとのことだった。異存はないだろうね?」
私に依存がある筈はなかった。エド・ルイスの最大のライバルであったジョー・ステッカーの実兄トニーは、当時のアメリカにおいて三本の指に入る大プロモーターであったし、レスラー間でステッカーの悪口を言う者は誰もいなかったからである。>(『鉄人ルー・テーズ自伝』ベースボールマガジン社)
ミネアポリス地区は、全米3大テリトリーのひとつであり、デビューしたばかりのテーズにとって「スターへの登竜門」だった。
トニーの弟、ジョー・ステッカーは「最後のシュート(真剣勝負)チャンピオン」といわれている。
<一九一七年には、ステッカーが正式なチャンピオンとして認知されるようになった。おそらく彼こそが、タイトル防衛戦で真剣勝負をした最後のチャンピオンだったろう。>(スコット・M・ビーグマン『リングサイド』早川書房)
これが本当なら、「悪魔の日本軍人」グレート東郷は、ジョー・ステッカーとは対極にいるプロレスラーだった。「ショーマン」の極致だったからだ。
当時、グレート東郷がミネアポリスでもメジャーな存在であったなら、ディック・レインズとも闘っていたはずである。
グレート東郷にとってミネアポリスは未知の領域であり、だからこそ、「初侵攻」のために「用心棒」大山倍達が雇われたのではないか?
であるなら、このときの大山は単なる「ボディガード」ではない。
真偽は不明だが、「ディック・レインズはトニー・ステッカーのポリスマンだった」という説がある(「ポリスマン」については「第5回」参照)。
レインズは、太平洋戦争真っ只中の1943年から約3年間、米軍で「実戦」を教えていた。
ディック・レインズとグレート東郷の初対決は「シュート(真剣勝負)」だった?
ここからは推測である。
若きルー・テーズを引っ張り上げたようにトニー・ステッカーは、「シュートに強い」正統派のレスラーを重用した。
ミネアポリスに乗り込んできたグレート東郷は、まさに正反対のショーマンだった。
トニー・ステッカーのディック・レインズへの指令。
「東郷とやらに身の程を思い知らせてやれ!」
ミネアポリス侵攻が「不穏なもの」になることは、グレート東郷も承知していた。だからこそ、「プロレスはできないがシュートなら誰にも負けない」大山倍達を雇い入れた。
必ず先にシュートで勝つ。ショーが始まるのはそこからだ(ルー・テーズ)
当時のプロレスが緊張感に満ちていた理由。
<関節技を使いこなせない限り、絶対に世界チャンピオンにはなれない。タイトルマッチともなれば、眼の色を変えた挑戦者は必ず私の逆関節を取って心理的に優位に立とうとする。それをさせたら、挑戦者を図に乗らせるだけだ。まず試合開始のゴングが鳴ったら、必ず先に相手を一度極めてしまう。そうすれば相手は“あぁ、テーズには敵わない”と諦めてしまうものである。>(『鉄人ルー・テーズ自伝』)
「必ず」先にシュートで勝つ。その闘いがプロレスラーの「格」を決める。ショーが始まるのはそのあとだ――。それがルー・テーズのプロレスだった。
グレート東郷の立場に立って推測してみる。
ディック・レインズとの闘いが完全な「シュート」になったら、自分は手も足も出ないだろう。大恥をかかされ、リングから逃亡しなければならないかもしれない。そうなれば、二度とミネアポリスに足を踏み入れることはできない。
客に飽きられたら荷物をまとめて次の街に行く――旅を宿命づけられたプロレスラーにとって、大きなテリトリーからの追放は死活問題となる。
こんなときのために脇に控えているのが「ポリスマン」である。
団体同士の初対決など「シュート」と噂された日本の試合を見てきたが、不思議なことにその多くがタッグマッチだった。そんなとき、注目すべきはスターの激突ではなく、タッグパートナー「用心棒」「ポリスマン」の闘いである。
不穏な空気が消えなかったから、グレート東郷は、トニー・ステッカーに対しこう釘を刺しておく必要があったのではないか?
「俺をなめるな!」
マス・トーゴーは、大一番の2日前にディック・レインズと闘った。
プロレス嫌いを公言していた大山倍達はアメリカ遠征の武勇伝を語らなくなったが、「ディック・リールは実在しない」と書かれたときだけ、激怒し、反証を試みた。
武道家としての誇りを傷つけられたから?
「ポリスマン」マス・トーゴーという存在を仮定すれば、話のつじつまが合うのは確かだが……。
大山倍達を包む霧は晴れない。闇はまだ闇のまま。
プロレスラー、マス・オーヤマとは何者だったのか?
私をバカだと言いなさい。私をウソつきだと書きなさない。
でも「ハゲ」と書いたら許さんからな!
大山倍達