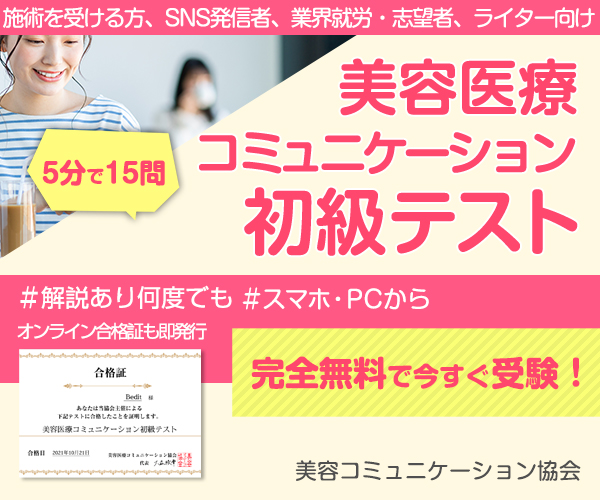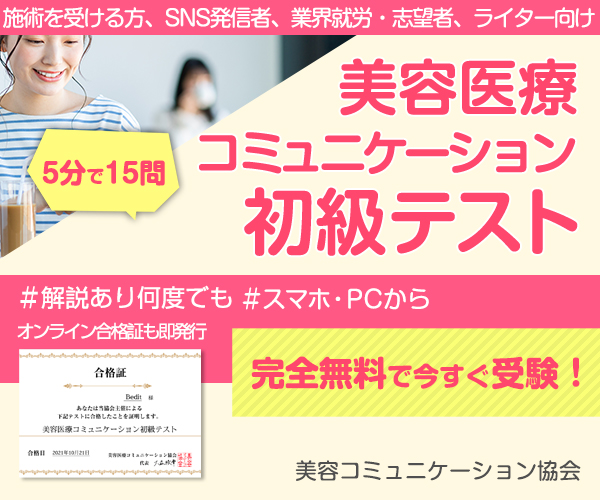

50年以上、テレビではまったく放映されない小人プロレス
史上最大の観客の前で試合を行った4人の小人レスラー。
リトル・トーキョー。ロード・リトル・ブリック。リトル・ビーバー。ハイチ・キッド。
会場のポンティアック・シルバードームの観客9万3173人。PPVの売り上げが1000万ドルを超えたというのだから、ひとつの契約が10ドルとして100万人以上(おそらく、その数倍)が彼らの雄姿を見たことになる。
2003年。リトル・ビーバーが「プロレスの殿堂」入り。翌年、赤羽茂(リトル・トーキョー)の親友で、アメリカ行きを強く勧めたというロード・リトル・ブリックが「プロレスの殿堂」入り。
書いていて「日米の温度差」に腹が立ってくる。
全盛期には毎夜のように試合が組まれ、客席を爆笑の渦に巻き込んだ日本の小人プロレスは、1960年代以降、一度もテレビ中継されていない。フジテレビは週末の午後に全日本女子プロレスを放映していたが、小人プロレスはまるで「なかったこと」のように編集され消された。
日本の小人レスラーは「見えない人間」なのだ。
舞台を全速力で駆け抜ける「爆笑王」ミスター・ポーン
小人プロレス界最大のスター、ミスター・ポーン。彼のプロレス人生のハイライトは、土曜8時の怪物番組『8時だヨ!全員集合』に初登場した瞬間だろう。
なんの脈絡もなく現れ、舞台を全速力で駆け抜ける。それまでの「作られた笑い」も進行上の取り決めも瞬時に破壊する力技。思考停止の解放感。
おそらく、何百万人がミスター・ポーンを記憶しているはずだ。
しかし、今、ネットを検索してもミスター・ポーンの経歴はどこにもない。彼がどんな死に方をしたのかすらわからない。
ミスター・ポーンこと猪瀬豊の少年時代の夢は、噺家か色ものの芸人になって寄席の舞台に出ることだった。
靴職人になった猪瀬は26歳のとき、道路でキャッチボールをしていた。
「プロレスをやってみないか?」
声をかけたのはのちの全日本女子プロレス社長、松永高司。
「いっぺん劇場に見にこいよ」
断る理由が見つからなかった。
「靴屋をやっててもね、日曜日に映画見に行って安酒場で一杯やるくらいしか楽しみはなかったしね」
松永に引っ張っていかれた場所は、スポーツとは対極にある暗がりだった。
前座の踊り子が舞台を去ると、急いで体操用シート6枚を敷く。1960年代後半。ストリップ劇場の幕間が小人レスラーの戦場だった。
それでもミスター・ポーンは断言した。
「プロレスはスポーツだ」
小人プロレスがスポーツでないなら、なんでこんな体になりますか?
1996年2月。引退し53歳になったミスター・ポーンは、電動車椅子に乗って待ち合わせ場所に現れた。
行きつけの喫茶店の一番近い椅子までの数メートルを、彼はものにつかまりながらゆっくりと歩いた。
「小人プロレスは、スポーツが半分、芸が半分だと思います。だって、スポーツじゃなきゃ、なんでこんな体になりますか?」
スカウトされた時期も遅かったが、デビューも遅れた。
「靴職人時代、木槌を持って背中を丸めていたから、人から教わった受け身じゃ背骨を痛めてしまう。試合中にボディースラムを受けて救急車で運ばれたこともある」
自分はレスラーに向いていないのではないか?
「それからは、自分に合った受け身を研究しましたねえ。技だってそうですよ。均整のとれた体つきのプリティ・アトムやリトル・タイガーの飛び技は、私ら、“ダックスフント”にはできません。上半身をビルドアップしての力技、お客の笑いを誘うやられ技を磨いていきました」
女子プロレスの人気が上がるにつれ、小人プロレスへの反応は鈍くなっていった。
「劇場でやってた頃は、客席からの声援も大きかったですよ。見てくれる人が違いましたから。ガキ相手のジョークではなく、大人のシャレがわかってもらえたからねえ。反応がビンビン返ってきた」
ビューティー・ペアの大ブレイクをミスター・ポーンは「会場にはガキしかいなくなった」と表現した。興行を追って旅をする女性ファンもいて、レスラー個々の「芸」を順番に出すプロレスは許されなくなった。
「今度はあれやるよ、とか、ここでひっくり返るよ、なんてヒソヒソ声が聞こえてくる。いろいろ工夫したけど受けなかったねえ」
アメリカのミゼット・レスラーはそんなハードなことはやっていない
最大の「工夫」は、スポーツの要素を増やしていくことだった。
「今思えば、それがいけなかったのかもしれない」
小人レスラーの身体には負担が大きすぎた。外人レスラーは口をそろえてこう言った。
「アメリカでは、そんなハードなことはやっていない」
小人レスラーは次から次へとリングを去っていった。
『8時だヨ!全員集合』出演は、小人プロレスの存亡を賭けたチャレンジだった。「市民権」獲得の闘争でもあった。
会場入りしたミスター・ポーンは、「何歩で駆け抜けるか」を計算し、リハーサルを繰り返した。ケガをしないぎりぎりの速度を探った。
客席は爆発し、茶の間の小学生は驚喜したが、テレビ局には抗議の投書が殺到した。
「優れた芸を見せるでもなく、ただ身体的に異常な人を見世物のように出すのは見ていてつらい」
「かわいそうだ」
「爆笑王」は、一瞬にしてブラウン管から消えた。