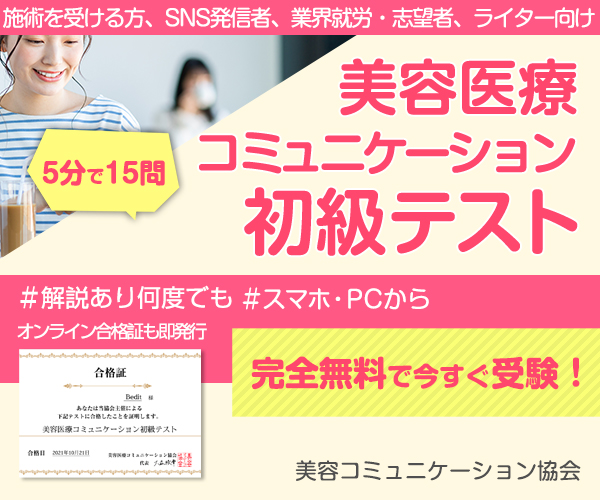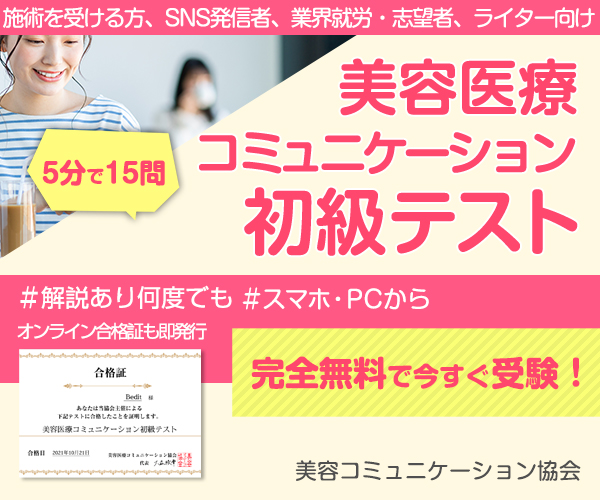

小人プロレスの孤塁を守り続けた3人の「小さな巨人」
「スポーツとしての小人プロレス」から離脱していったレスラーたち。
「男子」プロレスに対し激しい対抗意識を抱いて闘った完全無欠のベビーフェイス、プリティ・アトムは、目が見えなくなってリングを降りた。
アトムを反則攻撃でいたぶり続けたミスター・ポーンは、試合中に突然、足が動かなくなり、そのまま車椅子の生活に入った。
見た目のインパクトが強烈な名バイプレイヤー、天草海坊主は、リングの設営中に背骨を痛め、それが原因で走れなくなった。
1994年。オールスター戦が東京ドームで開催され、女子プロレスの人気が頂点に達したとき、リトル・フランキー、角掛留造、ミスター・ブッダマンは、全日本女子プロレスの自社ビル屋上にあった6畳一間のプレハブハウスで暮らしていた。
日本の小人レスラーは、3人だけになっていた。
東京ドームの花道。角掛留造が押す台車に乗って登場した「ザ・グレート・リトル・ムタ」ことリトル・フランキー。
対角線上に振られると、クルリと逆立ちして頭で滑りながら3メートルを移動する。頭を支点にコマのように回転する。客席のどよめきを呼ぶロープ最上段からのムーンサルトプレス。「世界最短」の足から繰り出される切れ味鋭いカンガルーキック。両足タックルで倒されると何度もバウンドする受け身の妙技「人間ゴム毬」……。
リトル・フランキーは、4万観衆を驚愕させ、爆笑させ、史上最大の女子プロレスの祭典を盛り上げた。「会場を温める前座の役割」を完全に超越する仕事だった。
「不世出の天才ミゼット・レスラー!小さな巨人!」(今井良晴リングアナウンサーの不変のコール)
リトル・フランキーの栄光は、その日が最初で最後だった。
会社にとって俺たちは“危険物”だから
全日本女子プロレスが「何もなかった」かのように旅の暮らしに戻ると、フランキーの出番が、1試合おき、2試合おきと、まるで歯が抜けるように減っていったのである。
その話を先輩のミスター・ポーンに振ると……。
「会社にとって俺たちは“危険物”だから」
危険物!?
「リングに上げたら死ぬんじゃないか、ってこと」
私がリトル・フランキー本人に体調を確かめようとすると……。
「今、体に悪いところはない」
話を遮られた。静かに叱られた。
「僕は肋骨を折ったぐらいで大きなケガもしていないし、病院に行くことも全然ない。『あと何年できるか?』なんて考えたこともないですよ。体が続くかぎりプロレスをやります」
しかし、その夜の彼の仕事はミスター・ブッダマンのセコンドだった。
リングを設営し、チケットやグッズを売り、場内整理をやり……ありとあらゆる雑用を引き受け、チャンピオンは旅を続けた。
1995年12月。私が最初に取材したのは神奈川県いすゞ自動車大和工場体育館だった。
リングサイドはガラガラ。そこだけ観客があふれている入場料1000円の立見席に「WWWA世界ミゼットチャンピオン」リトル・フランキーが声をかけて回る。
「あと千円出せば座れるよ」
全日本女子プロレスは年間250回以上の興行を打っていたが、そのころすでに地方興行のほとんどが赤字だったという。
治療など受けない。明日のリングのほうが大切だから
リトル・フランキーほどデビューが遅れた小人レスラーはいない。
小人プロレスの場合、入門前、なんらかのスポーツをやっていたレスラーは皆無である。
彼もそうだったが……。
「練習は、ジャイアント馬場さんやアントニオ猪木さんと変わらないと思います」
最初の課題、ヒンズースクワット100回をフランキーは10日でクリアした。いきなり才能を発揮したフランキーだが、会長となった松永高司は彼に問い続けた。
「お前、本当にプロレスができるのか?」
フランキーは間髪入れず「できます!」。その繰り返しだったという。
「あとで会長から聞きました。『怖さもあった』と。僕がちっちゃすぎるから」
私が取材をした1995年12月。小人プロレスは「終わりかけの世界」だった。
「小人プロレスをなくしたくはないけど、今の三人のうち二人がダメになったら、多分、潰れると思う。新人は来ない。街を歩いていても小人の姿を見かけなくなった。今は子どものときにわかったら、ある程度、治療できるようになっているみたいですね」
取材中、彼の試合は一度も組まれなかった。
リトル・フランキーは、リングで何を証明しようとしたのか?
次の言葉を残し、後楽園ホールの薄暗い廊下を去ってゆくリトル・フランキー……コスチュームが入ったでっかいバッグを背負った小さすぎる背中を今でも思い出す。
「僕は治療なんて受けませんよ。明日のリングの方が大切ですから。僕もポーンさんのように、体がぶっ壊れるまで闘うつもりです」